ミッション・ビジョン
癒やし&癒やされる社会の実現に向けて…

はじめまして。
代表理事の日なた みこです。
当協会のホームページにご訪問くださり、ありがとうございます。
『日本癒しびと普及協会』は、この世に生を受けたすべての子どもたちが、生まれてきてよかった!と、心から思える社会を目指して、1人でも多くのカウンセラーが日本で活躍することで、1つでも多くの命が救われることを願って活動する団体です。
2017年の公認心理師法施行により、日本においても、心理カウンセラーの国家資格が誕生しました。
しかし、職場環境や生活環境が複雑かつ多様化するなかで、生きづらさを抱える人たちは増加し、真に人の心に寄り添えるカウンセラーが、まだまだ足りていないのが実情です。
さらに、生きづらさを抱えるのは、大人だけではなく若年層にまで及んでいるのです。
子どもは大人を見て育ちます。
大人が笑顔でなければ、子どもの笑顔を育むことはできません。
そのために、『日本癒しびと普及協会』では、先ずは大人が笑顔になれるように、生まれてきて良かった!と思える人生を歩めるように、サポートできるカウンセラーを育成し、癒やし&癒やされる社会の実現を目指しています。
代表プロフィール

日なた みこ
MICO HINATA
1964年10月、南米ベネズエラ生まれ&湘南育ち。
大手IT企業に在職中、日本国政府派遣の海外ボランティア制度「青年海外協力隊」に、会社初の休職参加。
中米コスタリカ共和国にて、シンクロナイズドスイミングを指導。
2年間、開発途上国といわれる国に住む人たちとともに生活をする中で、「物質的な豊かさ=幸せ」とは限らないことを痛感。
帰国後、結婚して3人の男の子にも恵まれ、ワーキングマザーとして忙しくも充実した日々を過ごす。
同時に、兼ねてから興味のあった心理の学びをスタート。
その後、心理カウンセリングやコーチングの学びを重ねるなか、職場の上司の自死に遭遇。
引き留めることができなかった自分を責め、悲嘆の日々を過ごす。
しかし、自分を責めてばかりでは何にもならないと一念発起し、弔いの気持ちを行動に変える想いで起業。
心理職に大きく舵を切り、生涯のライフワークとする。
それから5年間、心理カウンセラーを養成する講座の講師として日本全国を巡り、年間50回以上の講座を開催して、のべ1万人以上の人と関わる。
現在は、「机上の空論ではなく現場主義」をモットーに、もっと身近に!もっと気軽に!もっと早く!カウンセリングが当たり前になる社会の実現に向けて、自身もメンタルクリニックで、心の病と闘う方々と年間300回以上のカウンセリングを行っている。
これらカウンセリング現場での経験から、『幸せマインド心理学®️』を開発。
併せて、「癒やしの才能」の開花させて、幸せを育むカウンセラーを育成する「癒しびと起業スクール」を運営し、カウンセラーの育成にも注力している。
協会専任癒しびと
日本癒しびと普及協会の活動に賛同する、認定癒しびとのメンバーを紹介します。
認定癒しびとは、『幸せマインド心理学®️』を習得して、プライベートレッスン I SMILE を担当します。

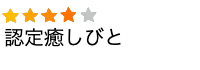
緑莉
MIDORI
1974年生まれ、北海道在住。
約30年事務職で働いてきましたが、もっと人に関わる仕事がしたいという思いがずっと心の中にありました。
ぼんやりと“カウンセラーになれたらいいのにな”との思いはあったものの、資格という壁で諦めかけていた時『幸せマインド心理学®️』に出会いました。
現在は、自宅サロンを開業し、“心とからだを整えて癒す”をコンセプトに癒しびととして活躍中。
メッセージ
誰もが生きていく中でたくさんの困難や問題に直面しています。
「どう乗り越えたらいいのだろう?」そう思ったことはありませんか?
そして、「なぜこんなことに…」とか「なぜ私だけ?」と、悲観的な気持ちになり、その思いが周りにも伝わってしまい、どんどんネガティブな悪循環に陥ってしまうことはありませんか?
その状態から自分の気持ちを立て直すのは、とても大変なことですよね。
そんな時は、誰かに話を聞いてもらうのが1番だと私は思っています。
出来事を言葉に出して話すだけでも、意外に心が軽くなったりします。
さらに、誰かに話すことで客観的な見方ができ、自分では思い付かない考えや解決策が発見できたりもします。
1人で抱え込まず、今ある感情を吐き出してください!
癒しびとの私が全力であなたの心に向き合い、笑顔で毎日が楽しいといってもらえるようサポートしていきます。

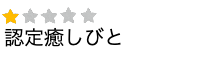
二宮 真理子
MARIKO NINOMIYA
1963年生まれ、神奈川県在住。
前職でカウンセリングを学び、私自身も、もっと早くカウンセリングを知りたかったと痛感。
改めて『幸せマインド心理学®️』を学び、カウンセラーをライフワークにすることを決意しました。
現在は、1人でも多くの方が、笑顔いっぱいで日々を過ごせるように寄り添い応援する癒しびととして活動中。
メッセージ
私は、結婚後間もなく母の自死や、子どもたちのジェンダー、不登校、夫のネグレクト、モラルハラスメント、離婚等、さまざまな出来事を経験し、その都度相談する方を探して乗越えてきました。
今振り返ると、もっと早くカウンセリングを知り受けたかったと思っています。
もし今、あなたの心が疲れ辛くなっているなら、私と一緒に心からの笑顔を取り戻し、明るい明日を見つけませんか?
私が、あなたに寄り添い、誠心誠意応援します。

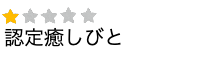
剣持 操
MISAO KENMOCHI
1971年生まれ、北海道在住。
子どもの頃から生きづらさを抱え、成人してからも2度の離婚でうつ病を発症。
現在は、心の病から復帰した体験と、弁護士にもお手伝いできないと言われた離婚問題を自ら解決した経験を活かし、心に寄り添いながら、難題を解決する癒しびととして活動中。
メッセージ
うつ病で仕事への復帰はできないと絶望していた私でしたが、お陰さまで今は、職場に復帰しています。
さらに、その経験を活かして、心の病から復職した人たちの相談を受けたり、各種ハラスメントの相談員として、職員の希望を見出すお手伝いをしています。
辛くて苦しいけれど、何が原因なのかはっきりと分からない。
問題が整理できていないし、そもそも問題が何かが分からない。
一生懸命頑張っているつもりなのに、なぜか周囲に理解してもらえない。
そんなあなたの問題を一緒に整理しながら、生きづらさを癒やし、自分らしい人生を歩みだすためのお手伝いをいたします。

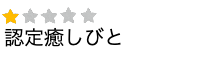
マナ
MANA
1970年生まれ、神奈川県在住。
離婚を経て、自分軸を立て直す!と、思った時に『幸せマインド心理学®️』に出会う。
現在は、人と関わる事が多い環境だった人生経験を強みに、心に寄り添いながら幸せマインドへ導く癒しびととして活動中。
メッセージ
夫の浮気が発覚した当時、子ども達がW受験という大事な時期だったので黙認して生活を継続していましたが、その期間は、私自身も心の葛藤にとても苦悩しました。
しかし、子ども達の為にも自分軸を立て直さなくては!と、思った時に『幸せマインド心理学®️』に出会いました。
2度とない人生、お悩み時間はもったいないです。
『幸せマインド心理学®️』であなたが癒やされ、そしてあなたの大切な人も癒やすことができれば、これからの人生は大きく変わると思いませんか?
まずは、私があなたに寄り添います。
一緒にお悩みを紐解いてまいります。
幸せマインドを手に入れて、本当のあなたらしい人生へ進んでいきましょう。

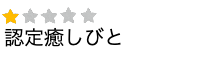
明津 尋子
HIROKO AKITSU
1962年生まれ、大分県在住。
第二の人生のスタート地点で、『幸せマインド心理学Ⓡ』と出会う。
これまでの人生で、どうしようも無かった思いを解決できる『幸せマインド心理学Ⓡ』を皆さんに知ってもらいたいと活動中。
メッセージ
真面目に頑張っている良い人に限って、心無い周囲の影響で、心が疲れきってしまったり、答えが見つけられずに、知らず知らずのうちに、自分を追い込んでしまったりしてしまう。
本当は全然悪くないのに…。
子どもの頃の親との関係、友人関係のトラブル、岐路の選択、職場での仕事、上司・同僚との関係、子育ての悩み、ママ友とのお付き合い、身体・健康の事、夫婦の関係、嫁姑関係等々の悩みはあるのに、弱音を吐けずに頑張っている人、戦ってる人、そして、自分が戦っている事にさえ、気が付かないままの人や心のどこかに蓋をしてしまった人など、『幸せマインド心理学®️』は、全ての人に知って欲しいと思います。
まず、私とお話ししませんか?
人に頼らず、ご自分の人生をご自分の選択で切り開いていく、そんなあなたになりましょう。
私が、精一杯寄り添わせていただきます。

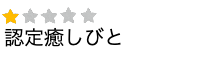
廣咲 華音
KANON HIROSAKI
1963年生まれ、東京都在住。
苦難・試練続きの人生で、第二の人生は志事を!と願った時『幸せマインド心理学Ⓡ』に出合う。
現在は、一人ひとりが自分らしく心豊かに、望む未来を創るサポートをする癒しびととして活動中。
メッセージ
「なぜ自分ばかり?」「どうして?」
人間関係に疲れ、介護に疲れ、父親の借金を抱え、体に不調が現れ、人生を諦めたらどんなに楽か!と思った時期がありました。
そんな辛い時一人で抱え込むのではなく、悩みを気軽に話せる環境があったら!と実感しています。
過去の重荷を背負い続けるのではなく、重荷を降ろし気づきを得て心を癒やしていくことで未来に向かっていけると思います。
命は有限。人生という時間も有限です。
幸せになることに遠慮はいりません。
一人ひとりそれぞれに「幸せのカタチ」があります。
人生の土台から幸せに、あなたらしく人生を心豊かに過ごせるようお手伝いします。
未来は自分で創るもの。一緒に未来を創っていきましょう。

田中 真智子
MACHIKO TANAKA
1968年生れ、福岡県在住。
看護師歴35年を経て、『幸せマインド心理学®』に出会う。
現在は、大変な人生を乗り越えられたからこそ、寄り添い、癒すことができる癒しびととして活動中。
メッセージ
私が悩み苦しんでいた過去があるからこそ、人の心の痛みに寄り添うことができます!
悩み苦しんでる人が、楽に生きられる方法がある事伝えていきたい!
苦しい過去を乗り越えた経験を活かしてカウンセリングをしたいと思います!
1人でも多くの幸せを願っています。

ほしの 里里
RIRI HOSHINO
1951年生まれ、大阪府在住。
海外在住約30年、家族で異国文化の中多くを学び、幸せな人生を送っていましたが、ある日突然離婚という思いもしなかった事で、私の人生は大きく変わってしまいました。
大荒波の大海の笹舟のごとく、先の見えない不安で一杯の十数年を経て、現在は、今を生きる事の大切さと生かされている事への感謝を伝える癒しびととして活動中。
メッセージ
人生では、いつ何時何が起こるかわかりません。
突然やって来るその大難の中、思い悩み、心と身体はさらに疲弊し、行き場のない不安や絶望や怒りに、進む道が分からなくなることもあります。
でも、今辛いことがあっても、過去には楽しい事もあった様に、必ずまた楽しい時がやってきます。
大切なのは、その辛い時をどの様に過ごすか。
そんな時…
寄り添い導き元気を与え、先を明るく照らす「ライトワーカー」の私と共に、今のあなたから新たな幸せな人生のあなたへと、変わっていきませんか?
変わっていきましょう!!
私がお手伝いいたします。
協会概要
| 名称 | 日本癒しびと普及協会(運営母体:株式会社 癒しびと) |
| 設立 | 2021年6月15日 |
| 代表理事 | 日なた みこ(磯野 美子) |
| 所在地 | 〒253-0082 神奈川県茅ケ崎市香川七丁目7番53号 |
| 電話番号 | *誠に申し訳ありませんが、カウンセリング中に営業の電話が多く来ることから、掲載は控えさせていただきます。 |
| メールアドレス | iyashibito.org☆gmail.com *☆マークを@に変更 |
《電話およびメールでのお問い合わせは受付けておりません。お問い合わせフォームよりお願いします。》
ロゴに込めた想い

ハスの花は、極楽浄土に咲く花とも言われ、花言葉は「清らかな心」「神聖」です。
カウンセラーは、人を癒やすことを目的に活動しますが、本人の心が癒やされていないと、人さまを癒やすことは難しいでしょう。
人の為と書いて、偽りと読みます。
この7色のハスの花のロゴには、先ずは、自分自身の心が癒やされ、そして、人の心を癒やせる「癒しびと」になって欲しい!
そんな願いを込めています。
SDGsへの取り組み
SDGsとは、2015年に国連サミットで採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)のことで、2030年を期限とする、先進国を含む国際社会全体の17の開発目標とそれを実現するための169のターゲットのことです。
株式会社 癒しびとでは、「日本癒しびと普及協会」事業の一環として、以下の目標に取り組みます。

CSR 社会貢献活動への取り組み
CSRとは、Corporate Social Responsibilityの略語で、日本語に訳すと、企業の社会的責任という意味になります。
一般的には、収益を求めるだけなく、環境活動、ボランティア、寄付活動など、企業としての社会貢献の活動を言います。
株式会社 癒しびとでは、「日本癒しびと普及協会」事業の一環として、この世に生を受けたすべての子どもたちが、生まれてきてよかった!と、心から思える社会を目指すビジョンのもとに、下記の団体を支援しています。
「NPO法人ブリッジフォースマイル」は、養護施設の子どもたちの一人立ちを支援する団体です。
児童養護施設や里親家庭などで生活する子どもたちの多くは、18歳で社会に巣立ちます。
親を頼れない子どもたちが、社会へ羽ばたく時に直面する「安心の格差」と「希望の格差」を乗り越え、未来へ向かう勇気を持てるような支援をカタチにする活動をしています。

法律相談に関して
「日本癒しびと普及協会」では、安心して相談できる環境づくりの一環として、法律に関わる相談事項に関しては、下記をご紹介しています。
谷川弁護士は、神奈川県弁護士会で自死遺族の支援を行う活動に取り組んでおり、自死に関わる法律問題を強みとする方です。
その他、消費者事件(詐欺や悪徳商法被害)では消費者の側に、医療過誤事件では患者側につき、立場の弱い方に寄り添っています。

